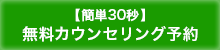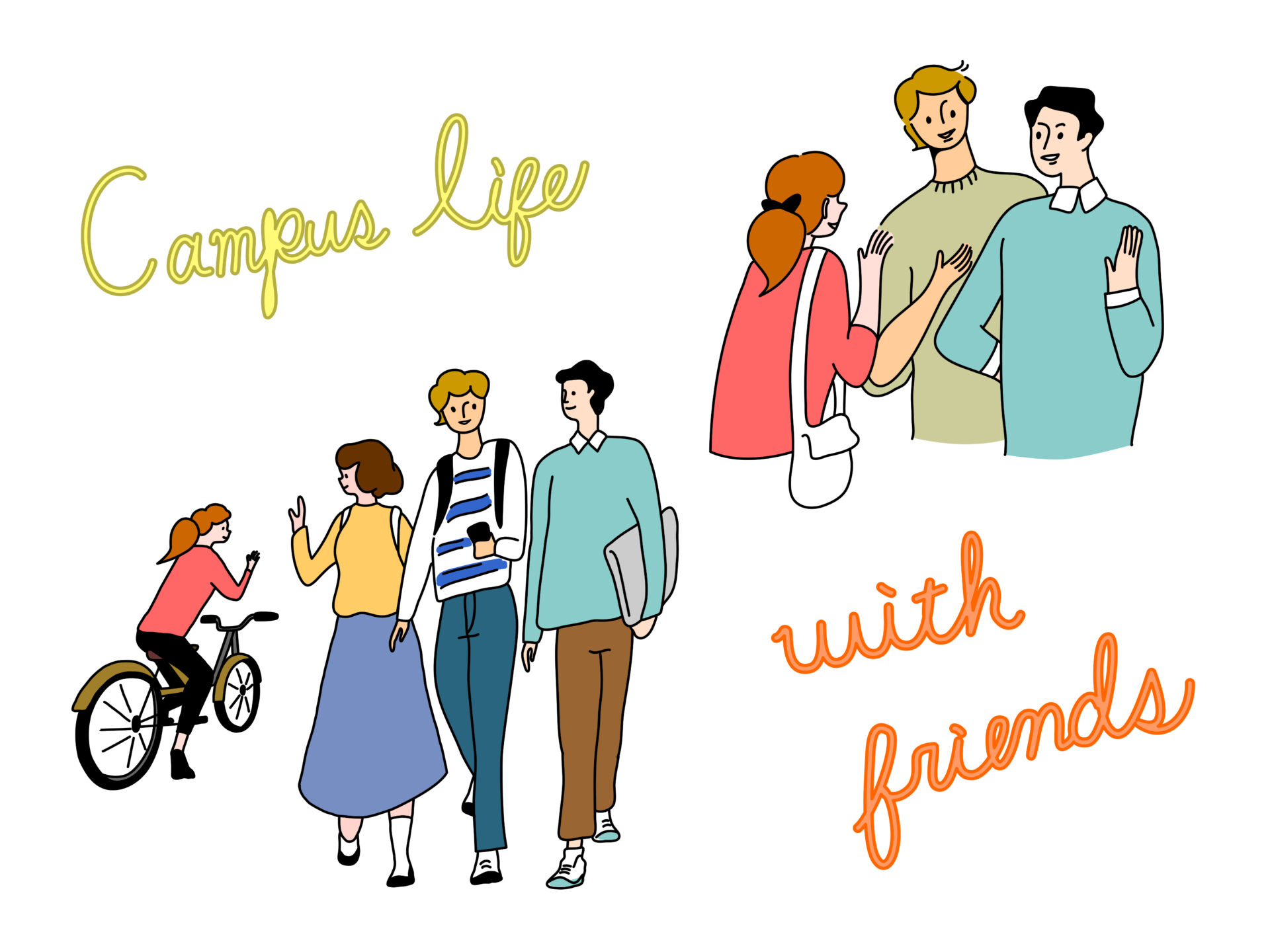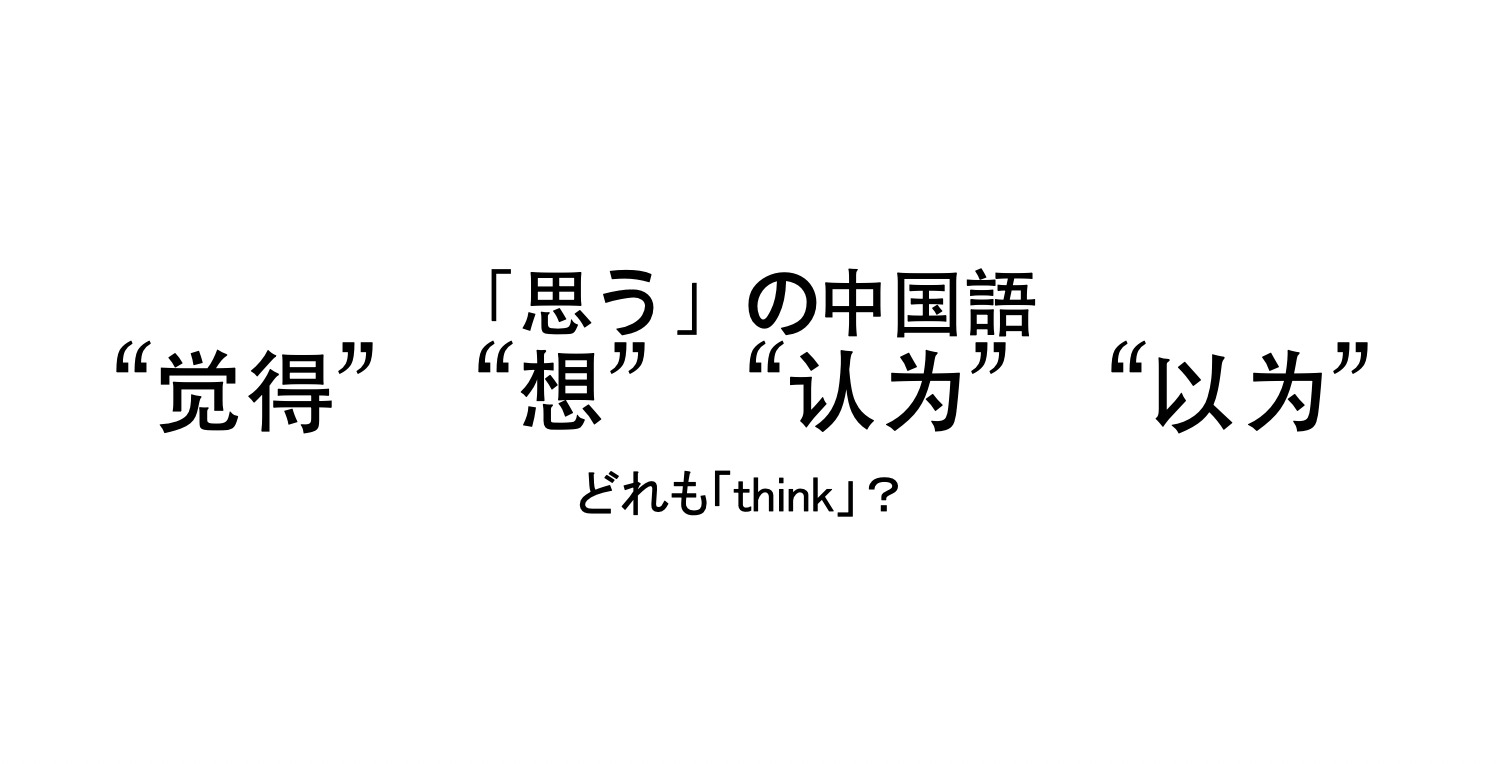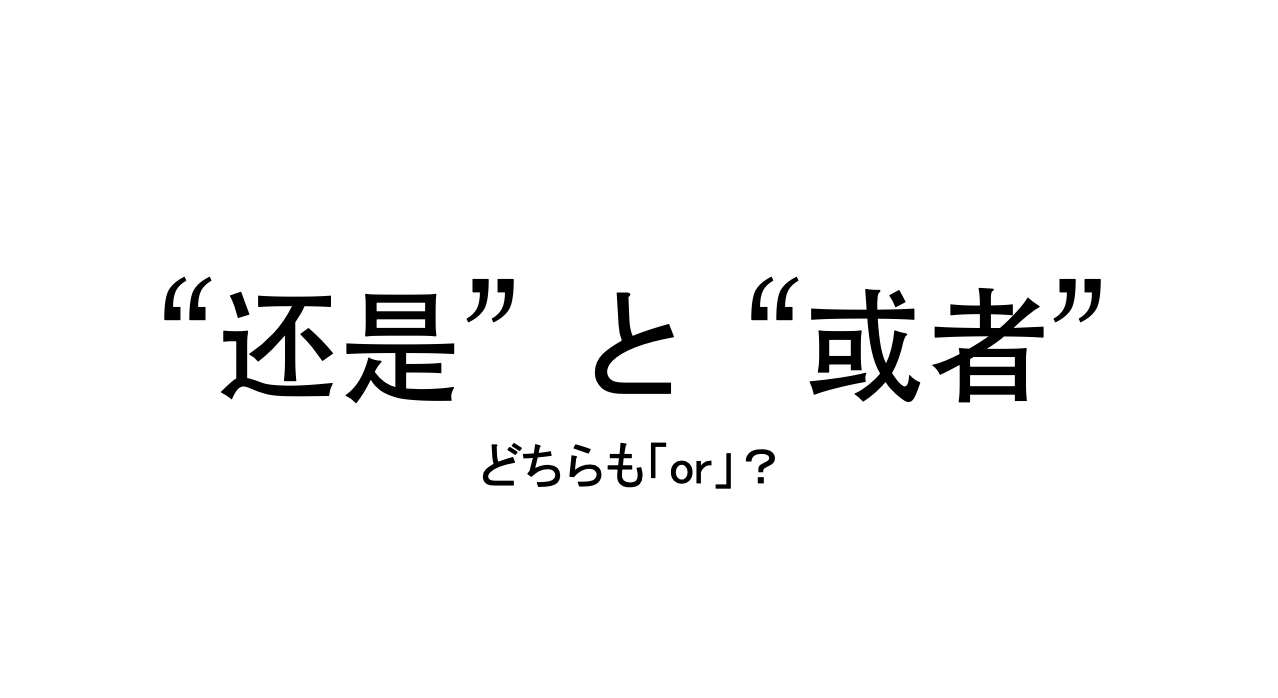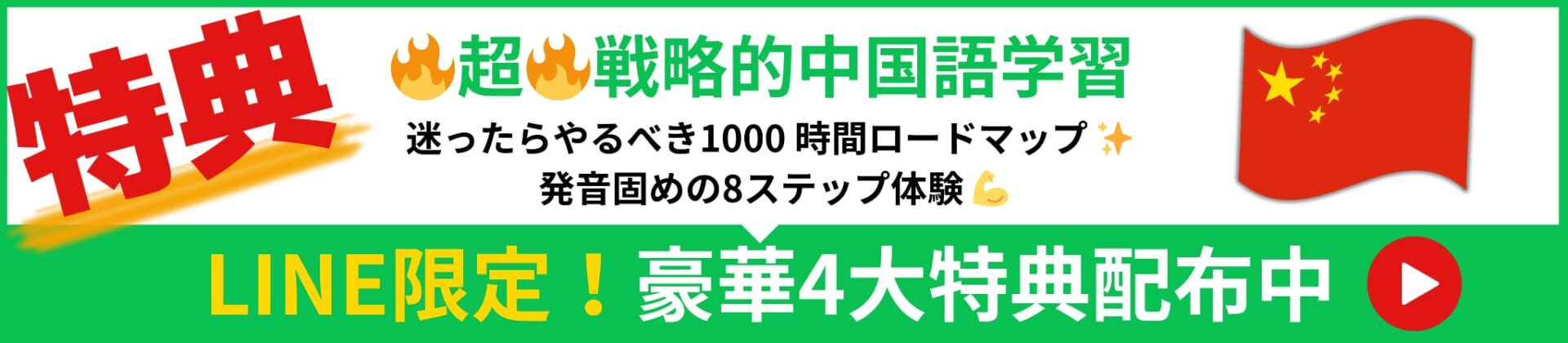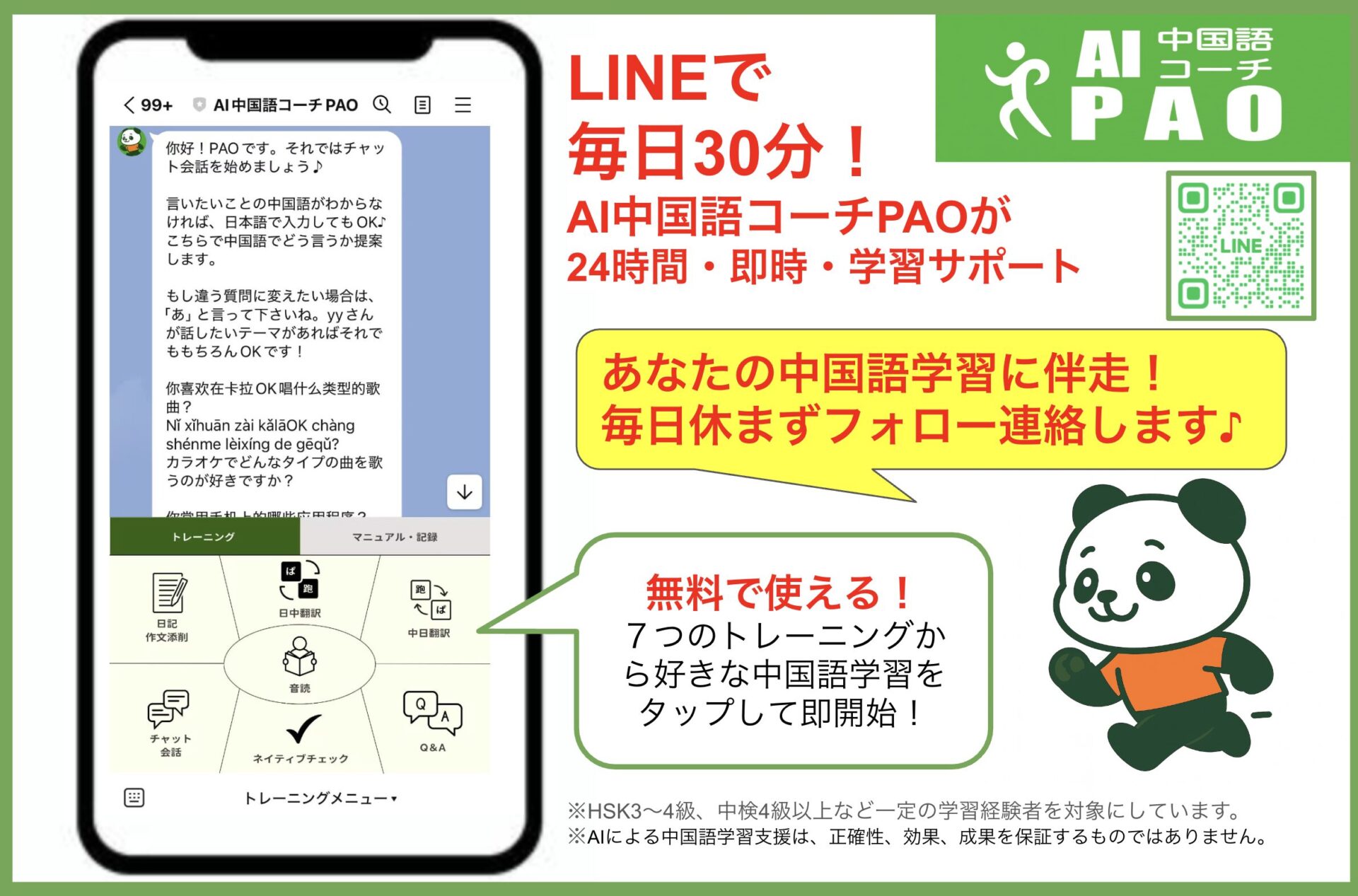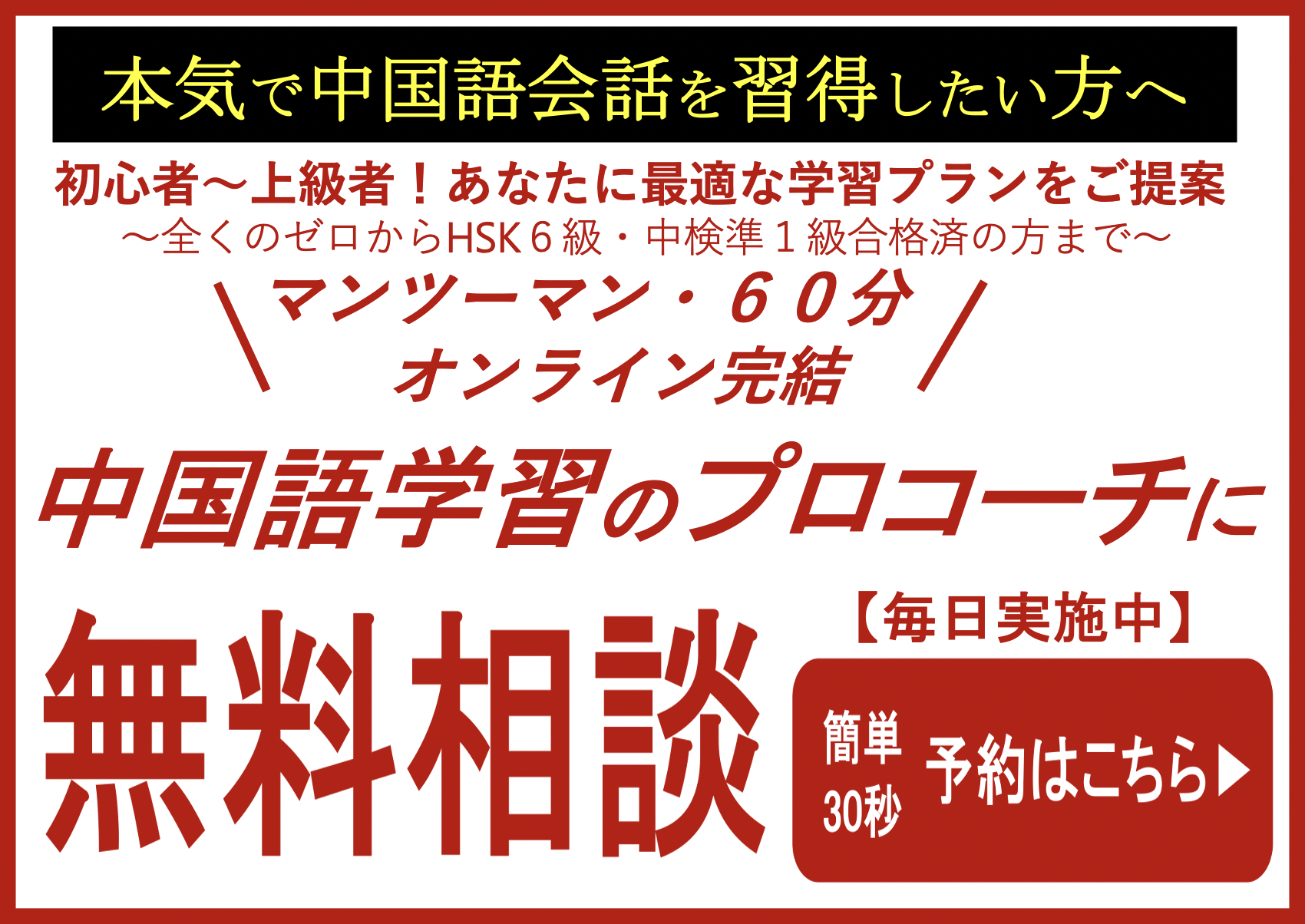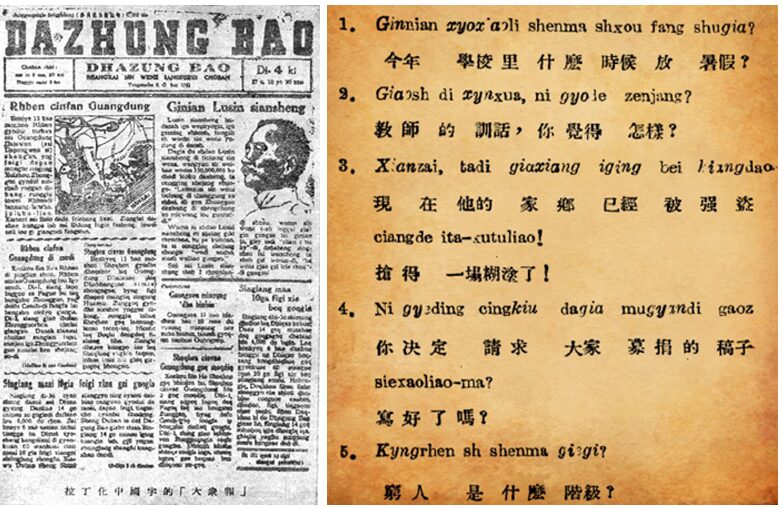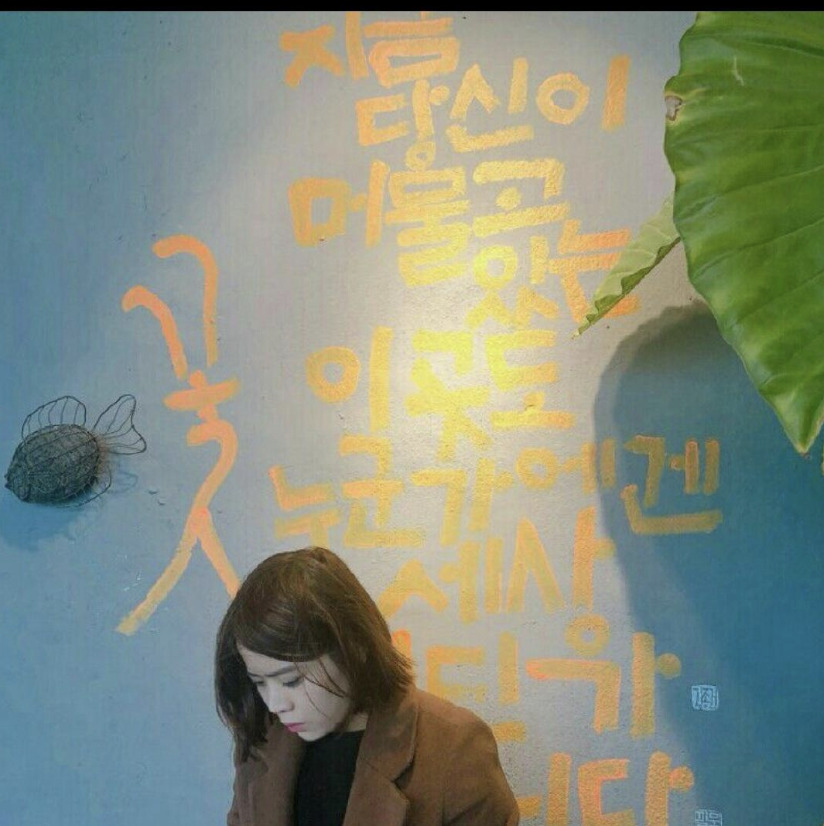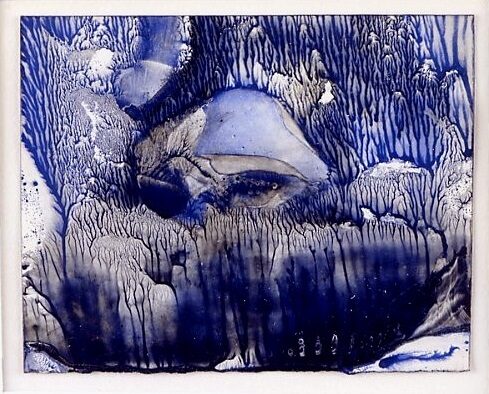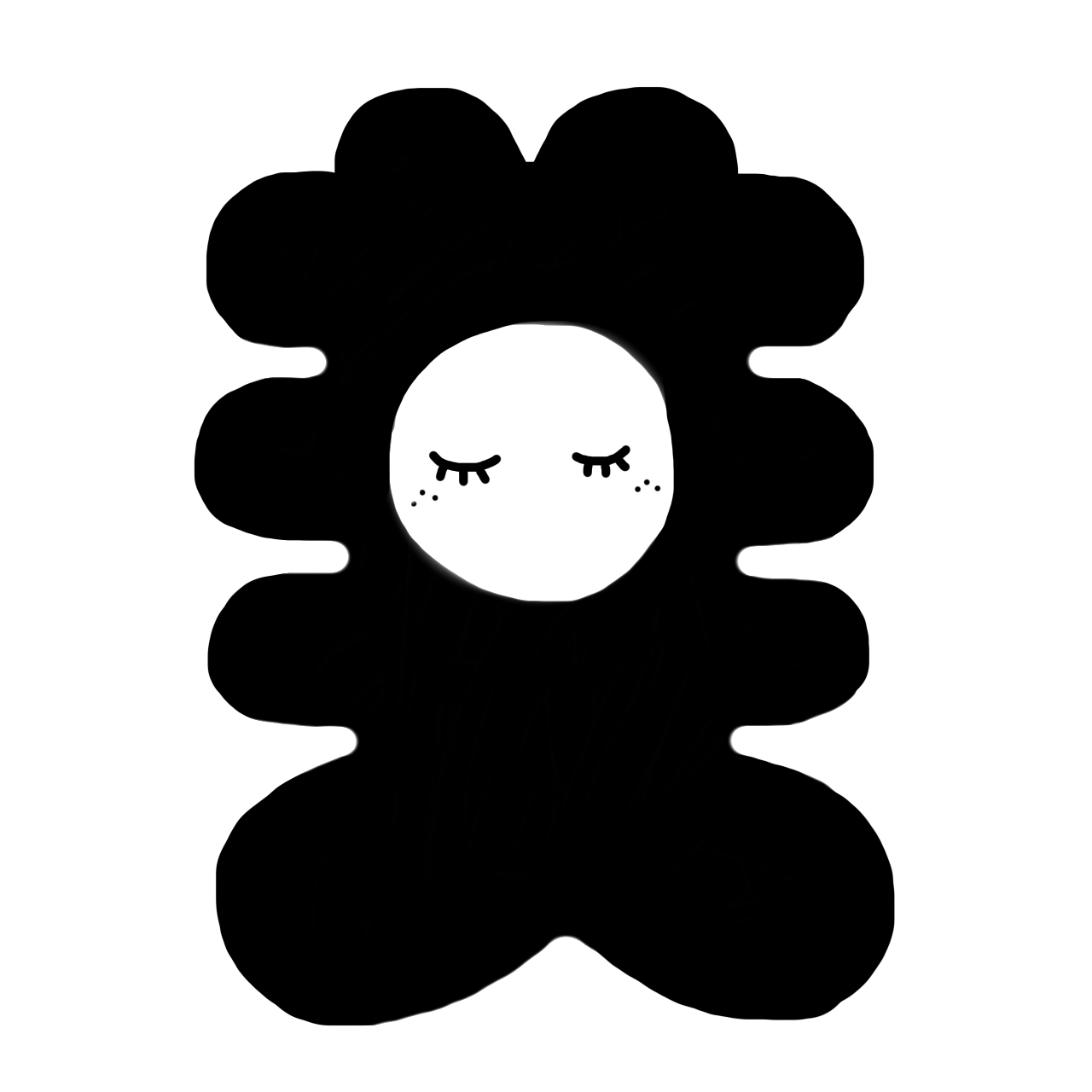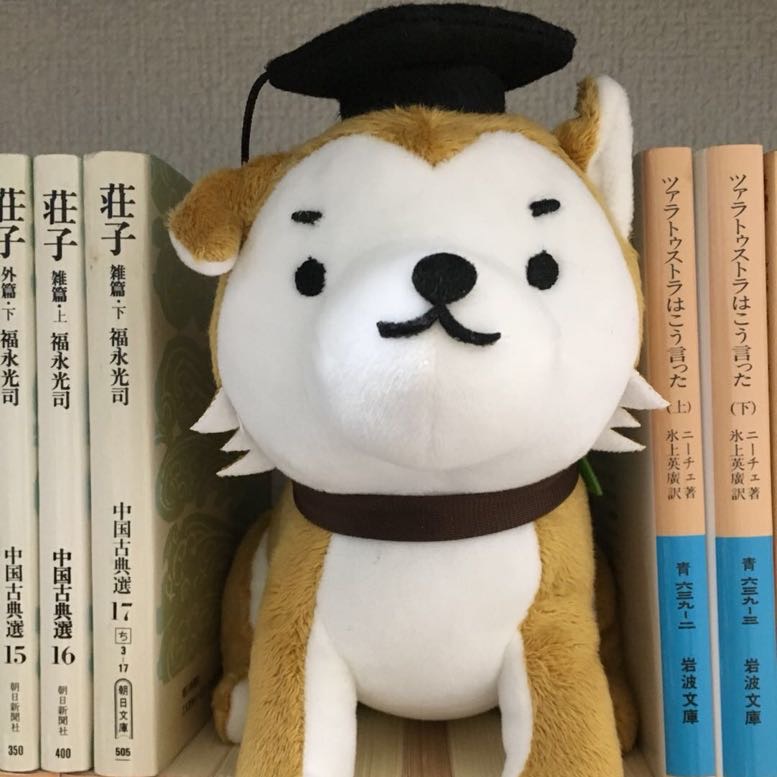【中国語】潘文国《字本位与汉语研究》の要約:10章の紹介と教育現場での応用


tad
千葉県出身、東京育ち。貿易関係の会社で10数年ほど勤務後、5年の中華圏駐在経験を活かして独立。現在は、翻訳や通訳などを中心にフリーで活動中。趣味はゴルフ。好きな食べ物は麻辣香锅。東京外国語大学外国語学部中国語学科卒業。中国語検定準1級。HSK6級。
tadさんの他の記事を見る関連記事
-

🎓 中国留学・滞在に役立つ!新学期に覚えたいキャンパスライフ中国語用語60選
-

スタバ(星巴克)で使える【中国語40選】商品名、注文、カスタマイズまで
-

【決定版】中国語のネット用語大全|Bilibiliで実際に使える50例文・ピンインつきでリアルな中国語センスを身につける
-

【中国語】「痛い」を表す表現「疼」「痛」「酸痛」「刺痛」「絞痛」「剧痛」「胀痛」の違いと使い分け!
-

中国語で乗りこなせ!【40例文】タクシー、バス、飛行機、電車の交通に関する便利なフレーズ集
-

【中国語】思う(think)を表す【觉得・想・认为・以为】はどう違う?
-

【中国語】“还是”と“或者”の違いを解説!どちらもorの意味ではないのか?
-

【中国語】違いは?<快、快要、要、就要…了>3点違いを押さえておこう
-

【中国語】「血」の読み方は3つ?「xuè」「xiě」と「xuě」
-

【完全保存版】中国語の相槌50個以上・10例文!会話が弾むリアクション表現まとめ